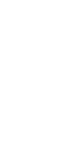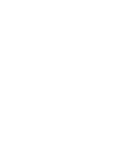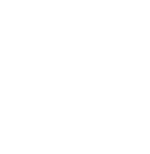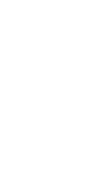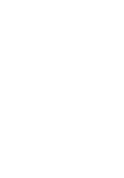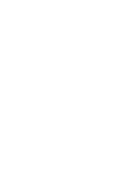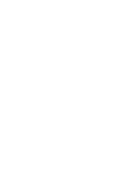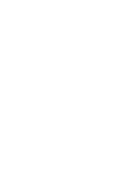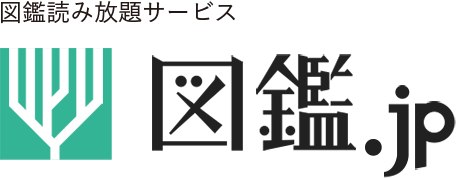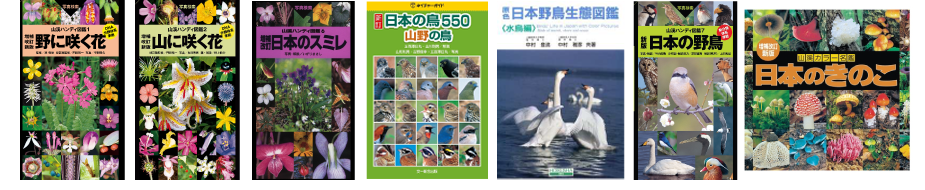今年こそ見分けたい!身近な植物識別講座
第4回 秋の里山で見られるシソの仲間
この連載では、掲示板でもお馴染みの小林健人先生(長池公園 副園長)が、ご自身の経験を交えながら、その季節によく見られる身近な植物の見分け方を教えてくださいます。
第4回目は"秋の里山で見かけるシソの仲間"です。
控えめな個性
秋は里山散策が楽しい季節。雑木林や野原にはアザミや野菊の仲間が点々と花開き、ガマズミやゴンズイなど、色付いた木の実も目に付きはじめます。また、谷戸の湿地や稲刈りを終えた田んぼの周りでは、ミゾソバやタデの仲間がひしめくように群生して、水辺を赤やピンク色に彩っています。少し注意深くアンテナを張って歩けば、どこか遠慮がちに花を咲かせているシソ科の植物を見つけることができるでしょう。四角い茎の先の方に、青や紫、淡いピンクなどの小さな花を複数付け、鋸歯(ギザギザ)のある葉が対になって付いているのがこの仲間の特徴です。また、葉を揉むと香りのする種類も多く、“シソ科”と聞くだけですぐにあの独特な香りを思い浮かべる方も多いかも知れません。
植物図鑑でシソ科のページをめくってみると、次から次へと似たような種類が出てきます。パッと見だけでも見分けられそうな種類は、花の付き方が独特のナギナタコウジュや、シソ科では珍しく淡黄色の花が咲くキバナアキギリなど、ごく一部でしょう。それら以外の全ての種の特徴を頭に入れるのは困難ですが、まずは開花時期や生育環境など、見た目以外の情報に注目することが大切です。たとえば、このコラムが公開されている10月時点で花が咲いているものは、シソ科全体のうちほんのわずかであることに気が付くはずです。今回は、野草図鑑の定番の一つとして知られる『野に咲く花』に掲載されているシソ科植物の中から、10月に関東周辺の里山でよく見られる在来種を厳選し、見分けのポイントを整理してみたいと思います。
青紫色の花が咲く2種
はじめにご紹介するヤマハッカとアキノタムラソウは、10月の里山で目にする機会の多い似たものどうしのシソ科植物です。いずれも、美しい青紫色の唇形花(※正面から見ると唇のように見える形状の花)を咲かせ、数~数十株がまとまって生えている点で共通しており、混同されることがあります。ヤマハッカの上唇(※正面から見た花の上側の片)には濃紫色の斑点があり、シソ科では珍しく先端が4つに裂けています。一方、アキノタムラソウの唇形花には模様が無く、花には短い毛がびっしりと生えている点が異なります。また、咲き始めには上を向いていた雄しべが、やがて下向きに曲がることも本種の特徴です。
このように、花をよく観察すると違いは一目瞭然なのですが、もう一つ、ぜひ着目したい見分けのポイントがあります。それは葉の形態です。ヤマハッカは、全ての葉が円形~楕円形の単葉で、基部は急に狭くなることが多く、柄に翼(ヒレ)があります。対してアキノタムラソウは、茎の下部の葉が3~7枚の小葉からなる複葉です。第二回のセンダングサのコラムでご紹介した『羽状複葉』と呼ばれる形を思い出していただければ、イメージしやすいと思います。つまり、茎の下の方に付く葉のかたちを見れば、両者はいとも簡単に見分けられるのです。
ところで、山地に出かけると、ヤマハッカに似て花の上唇に斑点の無いもの(コウシンヤマハッカ)や、雄しべと雌しべが花から飛び出しているもの(ヒキオコシ)などに出会います。里山で、ヤマハッカの特徴をじっくり見ておけば、これらの類似種と出くわしたとき、すぐさまその違いに気が付くことができることでしょう。
葉の脇に花が咲く3種
湿地や田んぼの畔など、水辺に目を向けてみると、十字対生(※真上から見ると葉が規則正しく十字型に並ぶ付き方)が特徴的な可愛らしいシソ科植物が目に止まります。シロネやハッカの仲間です。十字対生する葉の脇、葉腋と呼ばれる部分に花が集まり、段々に咲いて見えるのがこの仲間の特徴です。里山の水辺でもっともよく見かけるのがコシロネ。花は白色でわずか3ミリ程度しかないため、目立ちません。葉の陰に咲く本種の花を見つけた瞬間は、思わず感嘆の声を上げてしまいます。コシロネと比べれば見る機会は稀ですが、全体の雰囲気がよく似ているヒメシロネという種類があります。コシロネとは、葉の形の違いで見分けることができます。コシロネの葉は卵形で縁に粗い鋸歯があるのに対し、ヒメシロネの葉は細長く縁には細かくて鋭い鋸歯があります。また、ヒメシロネの葉の基部は急に幅が狭くなっています。
そしてもう1種、忘れてはならないのがハッカです。ハッカも葉の脇に花が付きますが、花数が多く、色も美しい紫色なので、シロネの仲間よりもゴージャスに見えます。独特な姿から、判別に迷うことはありませんが、ぜひ葉を揉んで香りを確認してみて下さい。皆さんもよくご存じの、あの爽やかなハッカ臭が辺り一面に漂ってくるはずです。
兄弟のようにそっくりなヒメジソ類3種
最後にご紹介するのはヒメジソの仲間です。名前のとおり、シソやエゴマとよく似た穂状の花序に、長さ4ミリ程度のごく小さな花を付けるグループです。葉っぱはシソよりもずっと小ぶりで、大きいものでも長さ5cm程度しかありません。これまでに紹介した種類は、一度見慣れてしまえば、パッと見の印象からでも種名が特定できるものばかりですが、次に紹介するヒメジソ三兄弟(イヌコウジュ・ヒメジソ・シラゲヒメジソ)はそう簡単にはいきません。Webサイトの写真や市販の図鑑でも、誤った種名を掲載している例があるほどです。そんな、初心者泣かせともいえるヒメジソの仲間ですが、ポイントさえ押さえてしまえば、誰でも確実に見分けることができます。里山散策で目にする機会も多いグループなので、ぜひ実物を観察しながらの識別にトライしてみましょう。ここでは、3種の識別ポイントを、①生育環境、②萼片の形態、③茎の毛の様子、④葉の形態の4つに絞り、順番に解説していきます。
①生育環境
3種の中で、もっとも見かける機会の多い種類はイヌコウジュです。道端、雑木林の林縁、草地、農耕地など、様々な環境で見ることができます。他種よりも、乾燥した場所を好む傾向があります。これに対して、ヒメジソは田んぼの畔や湿地、湿生草地など、イヌコウジュと比べてやや湿っぽい環境で見かけます。イヌコウジュとヒメジソが、いずれも日当たりの良い場所に生育するのに対し、シラゲヒメジソは、一名“ヒカゲヒメジソ”とも呼ばれるように、日陰の薄暗い環境に生育します。谷戸の湿地や放棄水田など、周囲に樹木が茂り、陽の光を遮っているような湿地帯に群生するヒメジソ類を見つけた場合、本種の可能性が高いといえるでしょう。
②萼片の形態
次に、花を包んでいる萼片に注目してみましょう。シラゲヒメジソの萼片には名前のとおり、白くて長い軟毛が生えています。他方、イヌコウジュとヒメジソの萼片は無毛か、わずかに毛があってもほとんど目立ちません。(※イヌコウジュの花序軸には短毛があります。)一般的に、萼片上唇の先端の尖り具合がもっとも鋭いのはイヌコウジュで、ヒメジソやシラゲヒメジソはやや鈍いとされていますが、尖り具合の強さには幅があり、たくさんの個体を見慣れないことには、この相違点だけで識別するのは難しいでしょう。
③茎の毛の様子
3種を見分ける際に重要なポイントとなるのが茎の毛の様子です。中でもシラゲヒメジソは特徴的で、萼片と同様、白くて長い軟毛が茎の稜(四つ角)に沿ってびっしり生えています。朝方や雨の日には、この軟毛に水滴が付いてよりわかりやすくなります。イヌコウジュの茎にも短い毛が生えていますが、こちらは稜だけでなく茎全面にまんべんなく生えるため、全体としてホコリを被ったように見えます。一方、ヒメジソの茎はほぼ無毛である場合がほとんどで、色も鮮やかな緑色を保ちます。私の普段見ているヒメジソは、茎が無毛でツルッとしているものばかりですが、中には稜の毛が目立つものもあるといい、毛の多少には幅があるようです。
④葉の形態
検索表などで、もっともよく採用されている区別点が葉の形態です。まず、イヌコウジュの葉には細かい鋸歯が6~13対あり、葉の基部は急に幅が狭くなる特徴があります。花穂のすぐ下に付く葉では、丸みを帯びた葉を付けることが多いことも良い目印です。次に、ヒメジソですが、本種の葉には粗い鋸歯が4~6対あり、葉の基部は少しずつ幅が狭くなるため、菱形のように見えます。また、イヌコウジュのように花穂のすぐ下に円形の葉を付けることはありません。シラゲヒメジソもヒメジソと同様、葉は美しい菱形ですが、こちらは鋸歯の数が6~11対あり、サイズもヒメジソの半分~3分の1程度とかなり小ぶりです。さらに、葉の表面には、手触りでもはっきりわかるほどの白い軟毛が生えています。
以上が3種を識別する主なポイントとなります。言葉での説明ではなかなか正確なイメージを伝えられませんが、何といっても、フィールドで実物を見比べ、標本やスケッチ記録をとるなど、地道に観察経験を積んでいくことが一番の早道です。ここではそれぞれの種について、葉のバリエーションをいくつかご紹介しますので、フィールドでの識別の際は、参考にしていただければと思います。
次なるステップへの招待
さて、今回は里山で比較的よく目にする在来種を厳選して取り上げました。しかしながら、実際にフィールドへ出てみると、農耕地から逸出したシソ、エゴマなど大型のシソ類や、マルバハッカ、ヨウシュハッカなどの外来種のハッカ類もしばしば見かけます。また、地域によっては、レモンエゴマ、トラノオジソ、フトボナギナタコウジュなど、この場で紹介しきれなかった低山地性の種類も見つかることがあるでしょう。これらは茎葉の毛や香りなどを丹念に調べる必要があり、さらに識別難易度の高い種群です。里山に自生するシソ科植物はもうバッチリ、という方は、次のステップとして外来種や山地性の種類の識別にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
ヒメジソの仲間の形態比較表(付録1)
|
和名 |
生育環境 |
萼片の形態 |
茎の形態 |
葉の形態 |
|
イヌコウジュ |
明るい乾燥した林縁など |
鋭く尖る |
短い毛を密生 |
基部は急に幅が狭くなり、鋸歯は6〜13対 |
|
ヒメジソ |
明るい湿った草地など |
尖りは鈍い |
無毛かまばら |
基部は徐々に幅が狭くなり、鋸歯は4〜6対 |
|
シラゲヒメジソ |
薄暗い湿地 |
白長軟毛あり |
白長軟毛あり |
表面に白長軟毛があり小型、鋸歯は6〜11対 |
秋の里山で見られるシソの仲間の主要学名一覧表(付録2)
ナギナタコウジュ Elsholtzia ciliata
キバナアキギリ Salvia nipponica var. nipponica
ヤマハッカ Isodon inflexus
アキノタムラソウ Salvia japonica
コシロネ(ヒメサルダヒコ ※1) Lycopus cavaleriei
ヒメシロネ Lycopus maackianus
ハッカ Mentha canadensis
イヌコウジュ Mosla scabra
ヒメジソ Mosla dianthera
シラゲヒメジソ(ヒカゲヒメジソ) Mosla hirta ※2
シソ(アカジソ) Perilla frutescens var. crispa f. purpurea
シソ(アオジソ) Perilla frutescens var. crispa f. viridis
エゴマ Perilla frutescens var. frutescens
マルバハッカ Mentha suaveolens
ヨウシュハッカ Mentha arvensis
レモンエゴマ Perilla citriodora
トラノオジソ Perilla hirtella
フトボナギナタコウジュ Elsholtzia nipponica
※1ヒメサルダヒコをコシロネと区別する見解もある。
※2シラゲヒメジソをヒメジソの変種とする見解もある。
小林健人(こばやし・たけと)
八王子市長池公園副園長。1987年神奈川県生まれ。多摩丘陵周辺の植物相解明をライフワークとしており、フィールドで過ごす時間は年間300日を超える。『新八王子市史』で執筆を担当したシダの仲間と外来植物が特に好き。