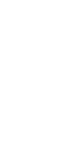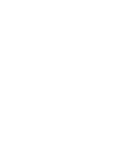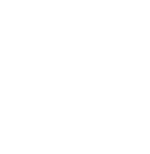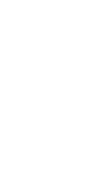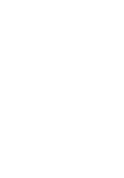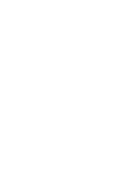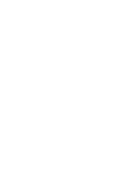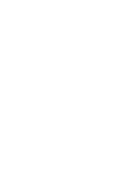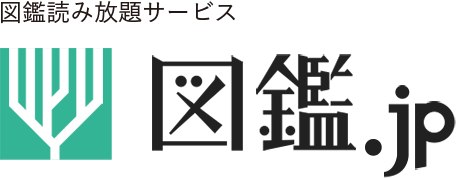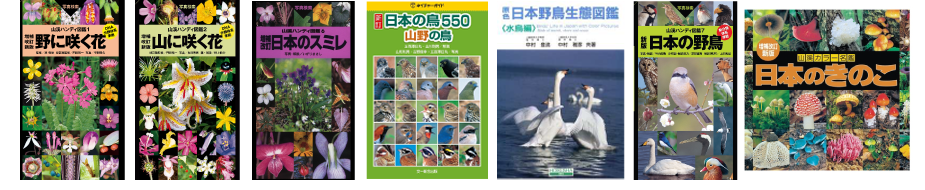永田芳男さんの日本全国花行脚
第21回 岩壁に咲く固有変種・ゲイビゼキショウ
『山溪ハンディ図鑑 山に咲く花』や『レッドデータプランツ』などでおなじみの植物写真家の永田芳男さん。髭がトレードマークで髭さんと呼ばれていましたが、いまでは髭も真っ白くなりました。三つ子の魂百までで、いまだに植物を追いかけて日本全国花行脚を続けています。旅先で出会った野生の草や木を主体に、時に花の名所なども兼ねて、永田さんが気になった植物をひとつずつ紹介していただきます。連載再開です!
ゲイビゼキショウはチシマゼキショウの変種で、確認されている場所はただ1ヶ所、岩手県の猊鼻渓(げいびけい)だけである。それも生えているのはひとつの岩壁だけ。同じような岩壁が連なる猊鼻渓の中でも、その岩壁以外では見ることができない。

写真=岩壁に生える希少種。環境省のレッドリストでは絶滅危惧IB類
希少なものの撮影では事前の調査や準備は怠らない。万全を期して撮影に臨む。まずその種の特徴。花茎や花柄が長い。花びらよりオシベが長い。などの特徴をメモする。既成の植物図鑑には写真が載ったことがないので、その場所で撮影したことがある友人がいないか、徹底的に調べる。幸いにして撮影したことがある知り合いが1人だけいた。いつ(何月何日)撮影したのか、現場の状況はどうか、などを丹念に聞いてから現場に向かった。

写真=猊鼻渓は岩手県一関市の砂鉄川にある
輝くような新緑の中を、猊鼻渓の舟下りの船は櫓をきしませながら進む。観光客との乗り合いの船である。上流の船着き場で客を降ろし、観光ポイントの大岩壁を見学した後に船は戻るのだが、その間の30分ほどの時間ではとても撮影はできないので、乗る時に帰りの船は別の船でとお願いしておいた。観光客と離れ、道のない急な斜面を登り、その岩壁に近づく。すぐ側には近寄れない絶壁なのだが、望遠レンズを付ければゲイビゼキショウが撮れることもわかっていた。

写真=右上に白い花が見える。左の個体は果実になっている
彼が撮影した日より早めに設定したにもかかわらず、花はすでに終盤だった。白い花が終わって緑色がかった果実がよく見え、花茎が20㌢ほどと高く伸びることも、花柄が1センチほどもある特徴が良くわかった。花をアップにしてみると、明らかに花被片よりもオシベの方が長いこともよくわかる。花びらの2倍ほどもオシベが飛び出しているものもあった。学名のvar. Geibiensis に納得した。

写真=オシベが明らかに長い
何とか撮影出来て、数年かけて調べた甲斐があったと喜んで、来た時とは別の船頭さんの船に乗った。これがまた大当たりで、帰りは説明することも少ないので船頭さんが櫓を漕ぎながら「げいび追分」を歌ってくれたのだが、その朗々たる歌声はプロも顔負けするほど見事なものだった。
2024年5 月25日 岩手県猊鼻渓で撮影。
★図鑑.jpには掲載図鑑はありません。
ゲイビゼキショウ
Tofieldia coccinea var. Geibiensis
チシマゼキショウ科