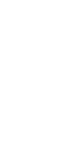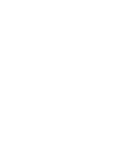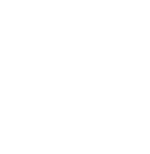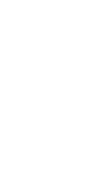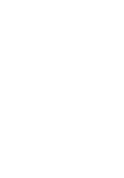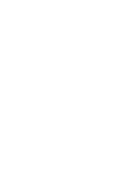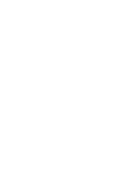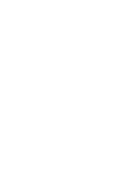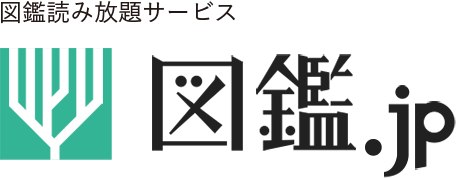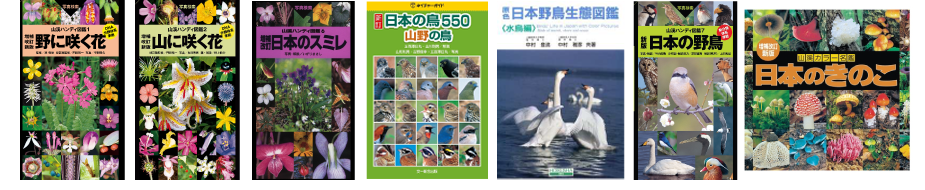永田芳男さんの日本全国花行脚
第22回 謎の新種オオミヤマウズラ
『山溪ハンディ図鑑 山に咲く花』や『レッドデータプランツ』などでおなじみの植物写真家の永田芳男さん。髭がトレードマークで髭さんと呼ばれていましたが、いまでは髭も真っ白くなりました。三つ子の魂百までで、いまだに植物を追いかけて日本全国花行脚を続けています。旅先で出会った野生の草や木を主体に、時に花の名所なども兼ねて、永田さんが気になった植物をひとつずつ紹介していただきます。
ランの仲間であるオオミヤマウズラは長い間ミヤマウズラと混同されたままだったが、2008年の植物分類学会で芹沢俊介愛知教育大学教授によって新種と発表された。正式な論文は書かれていないため、学名は Goodyera sp. となっていた。
2009年に発行された『レッドデータブックあいち』においても学名はこのままである。オオミヤマウズラはミヤマウズラとシュスランの雑種の可能性があり、翌年の2010年に韓国の済州島産の標本を元に、韓国で先に論文が発表された。このときの学名は Goodyera × tamnaensis である。ただこの論文をみる限り、描かれた絵や、写真を見ると葉に明らかな白い斑紋がある。葉に白い斑紋が出るのはミヤマウズラの特徴である。愛知県に多いオオミヤマウズラには白い斑紋は出ないが、稀に出るものがあるので、はて…と困ってしまったのである。
写真=ようやく撮影ができたオオミヤマウズラ
芹沢先生の論文には、愛知県内で採集された標本を元にオオミヤマウズラの解説が書かれている。草丈は25~40㎝、常緑で茎の下部は地を横に這う。ミヤマウズラとの何よりの違いは花期で、オオミヤマウズラはミヤマウズラより花期が半月ほど遅い。花の数もミヤマウズラよりも多く、花の構造も違う。花は平開しないのである。萼片にはおびただしい腺毛が生え、花をアップで撮影するとこの腺毛は顕著である。また側花弁の先端に緑色の斑紋が出るので、これが目玉のように見えるのもオオミヤマウズラの良い特徴である。また唇弁の先端にもやや薄いが緑色の斑紋が出る。この斑紋は花がすがれてくると褐色に変わるが、ミヤマウズラのような赤褐色ではない。
写真=花の繊毛がわかりやすい
わたしは『レッドデータブックあいち』に関わっていたので、事の成り行きを最初から知っている。ミヤマウズラとは違うランの花が咲いていることにわたしの友人のひとりが気がついていた。彼が見つけたその場所で写真を撮りたかったのだが、その場所では花が咲かなくなってしまった。彼は研究熱心で、四国でガクナンと呼ばれているランが、どうも同じものらしいというところまで、芹沢先生が発表する前に調べていた。色々と調査してみると関東地方南部あたりから、三重県にかけて分布すること。四国や九州にも同じものがあるらしいことなど、色々なことがわかっていた。
しかし、わたし自身はそのオオミヤマウズラを見たことがないので、ごく親しい友人が花の咲く自生地を知っている、と言うので昨年からお願いしておいて、今年になってやっと実物を撮影することができたのである。花が咲いた全体を見た第一印象は「ミヤマウズラではない」だった。葉が厚く白斑がない。草丈が結構大きい。そばで花を見ると緑色の目玉がある。などなどミヤマウズラとはまったく別物に見えてきた。なるほど確かにこれは違う、となったのである。
写真=緑色のふたつの目玉が特徴
韓国産のものとは違うのではないかと思っていたが、その後、2022年になって神戸大学の末次健司教授がオオミヤマウズラとして新種発表していることを知った。学名はGoodyera crassifolia である。crassifolia とは「厚い葉の」という意味である。
写真=「葉が厚い」が種小名の由来となった
はじめて花が撮影できて、疑問に思っていたことも解決して、まさに万々歳である。ちなみにミヤマウズラの花のアップは、拙著「山に咲く花」(山と溪谷社)に載せてあります。オオミヤマウズラが載っている図鑑はまだないと思います。
2025年9月22日、愛知県で撮影。
永田芳男(ながた・よしお)
1947年生まれ。植物写真家。おもな著書に『山溪ハンディ図鑑 山に咲く花』『増補改訂新版 絶滅危惧植物図鑑レッドデータプランツ』(いずれも山と溪谷社)など多数。
★図鑑.jpのオオミヤマウズラの掲載図鑑
ミヤマウズラのプレビューページ
https://i-zukan.jp/category/syu?category_id2857